里山資本主義 藻谷浩介&NHK広島取材班著 角川書店
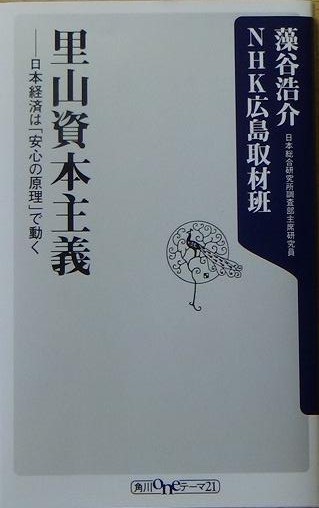
- [はじめに」で、この本の言いたいことがまとめてある。
今の経済は資源を豊富に使い、グローバル経済システムを追う、アメリカ流のマネー資本主義であり、 それは2008のリーマン・ショックで破綻した。不安、限界を抱えるマネー資本主義に対抗し、 里山資本主義はマネーに依存しないサブシステムで、水+食料+燃料を金が乏しくとも手に入れる仕組み。 GDPや成長率につながらないが、安全安心の価値を生む。過疎地域でこそ可能性が大きい。
- 「第1章」では 中国山地真庭の銘建工業(中島社長)はバイオくず活用で1万KWバイオ発電と
ペレット熱利用(Kiro20円販売)している。庄原市和田芳治のエコストーブはペール缶で作った薪ストーブ
だる。高齢者は光齢者で、省エネは笑エネだという。
- 「第2章」では 里山資本主義を地で行きユーロ危機と無縁な超優両国オーストリアの紹介。
ペレットボイラーのエネルギーコストは灯油のは50%コスト(灯油1リッター80centがペレット2kg 相当40cent)。但し、ペレットボイラ設備が?10000に対し石油ストーブは?3000-4000安い。
ギユッシング(人口4000人)は地域暖房化でエネルギー自給率72%となり、13年間で50企業が来て 1100人の雇用が増え、税収は?34万/1993年→?150万/2009に増加。CLT(cross laminated timber) による木造高層建築も狙う。
地域暖房が何故出来たかは「1990年に化石燃料からバイオ燃料への転換を地域経済再生の切り札として議会で 決定した事」
・・・市街地と産業施設をバイオマス地域暖房+熱配管35kmで網羅。
例えば、950人への地域熱供給システムの?1000万建設投資を住民投票で決め、運営も自主管理。
(滝川薫、100%再生可能へ、欧州のエネルギー自立地域 参照)
バダシュ市長は「大事なのは住民の決断と政治のリーダーシップ」と言う。 - 「中間総括(藻谷浩介)」では 国が出来ない事を地方でやる。日本の各地方がオーストリア(人口1000万)を
実現すれば良い。里山資本主義は地域経済自立と安全保障をもたらす。マネー資本主義へのアンチテーゼであり、
①「物々交換」「木くず→電力」はGDPを生まないが価値、幸せがアップ
②規模の利益、分業原理への異議。
日本の失業率は低く見えるが実は13%と高い(雇用調整助成で6%に下げている)。これは年寄りを助け若者 にしわ寄せが行っている。林業は失業率を改善できる。
- 「第3章」では 里山資本主義の例を多く述べている。高知モデルは大きな森林面積84%を活かし大豊町に
製材所と発電所を建設など。「第4章」では 里山資本主義は 無縁社会を克服できるし、精神的豊かさも得られる
という。「第5章」では 高齢者ばかりの無縁社会の都会と過疎の田舎は似ている。次世代産業の最先端と里山資本主義の
志向は似ている。スマートグリット技術はピーク制御技術であり、スマートシティ技術は地産地消のエネルギー自立
を狙うもので、日本の得意なしなやかな技術であり、里山資本主義に共通する。都会のスマートシティ技術と地方の
里山資本主義は車の両輪となろう。
- 「最終総括(藻谷浩介)」では マネー資本主義の先行きに不安、限界を感じるが、里山資本主義は
金が機能せずとも水+食料+燃料が手に入るのでマネー資本主義をバックアップできるシステムだと説く。
少子化問題は大都市、北海道など子育てしにくい地域(通勤、労働時間、保育所)ほど少子化がひどいが、一方 マネー資本主義で取り残された日本海側、日本南部は出生率が高い。これは少子化はマネー資本主義の未来不安 の結果であることを示しているのではないか? 里山資本主義は少子化を止めるられるし、健康寿命をのばし、 明るい高齢者社会を作る、食料自給率もエネルギー自給率もアップしよう。
本書の述べている通り、マネー資本主義は行き詰まりがあり、里山資本主義が大きなシェアを
占めるようになって欲しいと思う。然しながら本書と同じような林業活性化に依る地方活性化、分散型経済の
必要性については過去にも叫ばれてきたにも拘らず、日本では未だ大きな進展を見せていないのは何故だろうか?
私は「里山資本主義」という命名は素晴らしいし主張していることも尤もと思うがきれい事の精神論を述べている
にすぎないと感じ、この本の主張により里山資本主義が進展するとは思えない。
より大事なことは、どうして日本では里山資本主義が進展しないのか?其の理由を突き止め、早く西欧諸国
並みに里山資本主義のシェアを上げるにはどうすればよいかを追求することだと思う。
私は其の理由は 日本の林業やバイオマスエネルギー化が補助金に頼り何とかやっている状態であり、この本
に登場する例もほとんどは補助金無しでは経済的に自立はできないと考えるか、経済的に成立するものにして
いないことにあると思う。
しかし西欧では経済的に成立して石油の半分以下のコストを実現しているのである。しかも資源条件的には
日本のほうが有利なのである。徹底的に西欧を学び、何が西欧と違うのか分析し日本でどうすべきかを検討する
必要がある。私は以下の2つが重要だと考える。
第一に林業で生産したものをしっかり活用する仕組みの構築である。具体的には林業で生産したバイオマスチップや
ペレットを活用する地域熱供給システムを構築すること。分散型のシステムであり其の地域にマッチングした大きさの
地域熱供給システムを構築することをサポートする組織が必要でしょう。石油の半分以下のコストが実現できるなら
自ずから地域住民は自らの暖房を石油からバイオマスに置き換えるべく地域熱供給システムに参加するだろう。
第二は其の安いコストの実現である。林業のコスト、バイオマスエネルギーのコストに関して何が西欧と違うのか
分析し日本でどうすべきかを検討すれば必ずや西欧並みのコストを実現できるはずである。この場合、あくまで補助金
を前提としないで目標コストを実現することである。日本の場合補助金に溺れて真に安いコストが追求できていないと
思われる。